いたや内科クリニックブログ
CLINIC BLOG
-
- いたや内科クリニックブログ
- 東中野のクリニックで治療を検討している方へ[高血圧の原因・メカニズムとリスク、治療法]
東中野のクリニックで治療を検討している方へ[高血圧の原因・メカニズムとリスク、治療法]
2025.05.12
高血圧は、さまざまな病気の原因になる症状であるため、クリニックを受診して早期に改善することが望ましいとされています。この記事では高血圧の原因やメカニズム、リスク、また東中野の各クリニックでもおこなわれている治療法についても解説します。
東中野のクリニックで治療を検討している方へ[高血圧の原因・メカニズムとリスク、治療法]|高血圧の主な原因(一次性高血圧と二次性高血圧)
東中野のクリニックで治療を検討している方へ[高血圧の原因・メカニズムとリスク、治療法]|血圧が上がるメカニズム(交感神経系・ホルモン・血管抵抗など)
東中野のクリニックで治療を検討している方へ[高血圧の原因・メカニズムとリスク、治療法]|高血圧を放置すると起こりうる健康リスク
東中野のクリニックで治療を検討している方へ[高血圧の原因・メカニズムとリスク、治療法]|高血圧の主な治療法
東中野のクリニックで治療を検討している方へ[高血圧の原因・メカニズムとリスク、治療法]|おわりに
東中野のクリニックで治療を検討している方へ[高血圧の原因・メカニズムとリスク、治療法]|はじめに
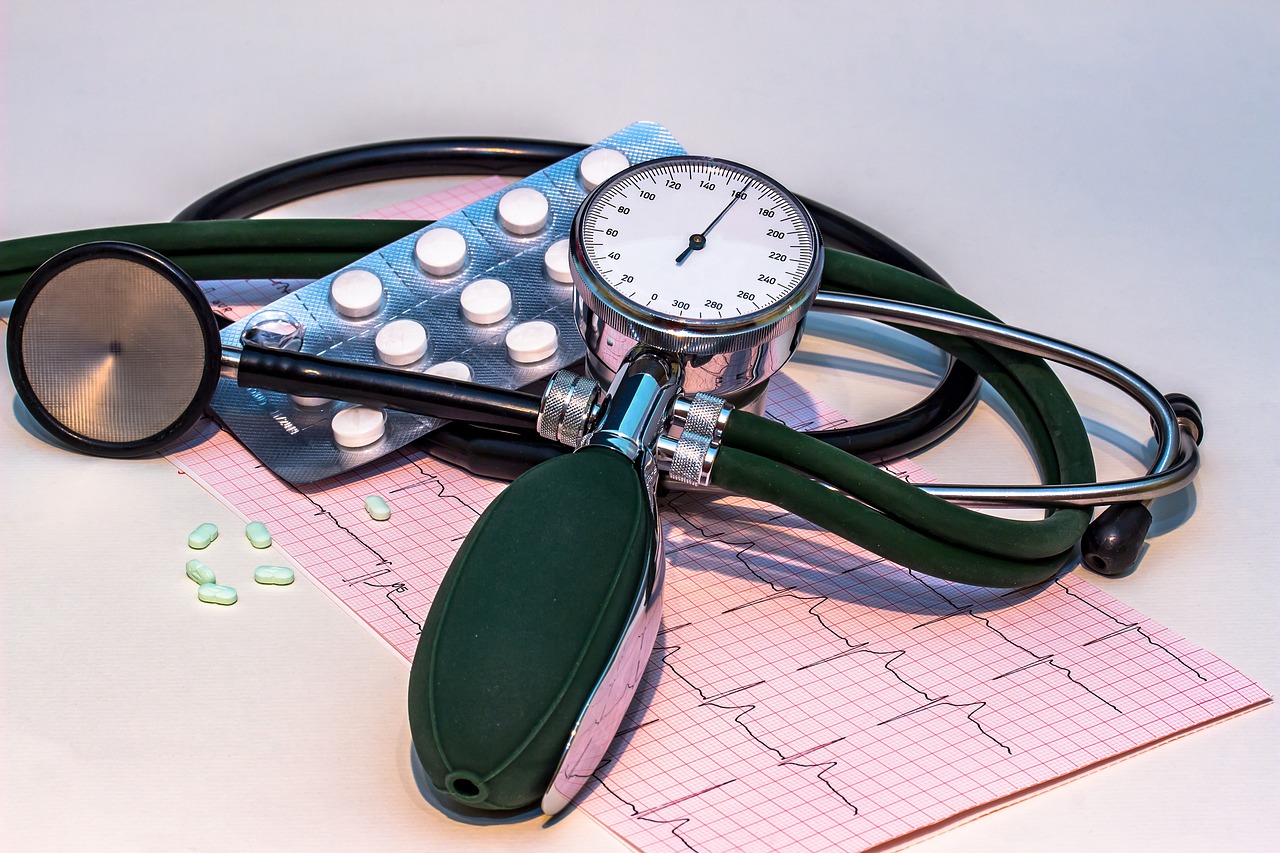
高血圧は日本人の多くが抱える生活習慣病でありながら、自覚症状に乏しいため見過ごされがちです。
しかし、放置すれば脳卒中・心臓病・腎不全といった重大な合併症の引き金にもなります。
高血圧には原因が特定できない「一次性」と、病気などが背景にある「二次性」があり、それぞれ適切な対策が求められます。
本記事では 高血圧の仕組みや原因、リスク、東中野の各クリニックでも対応している治療法についてわかりやすく解説します。
なお高血圧については、東中野にある当クリニックのブログ記事もあわせてご参照ください。
東中野のクリニックで治療を検討している方へ[高血圧の原因・メカニズムとリスク、治療法]|高血圧の主な原因(一次性高血圧と二次性高血圧)

高血圧には、大きく「一次性(本態性)高血圧」と「二次性高血圧」があります。
一次性高血圧は全体の約90%を占め、明確な病気による原因がないタイプです。遺伝的な体質に加え、生活習慣の積み重ねが要因となり、例えば下記が血圧上昇の誘因になります。
- 塩分の摂りすぎ
- 肥満
- 過度の飲酒
- 運動不足
- ストレス
特に日本人では食塩の過剰摂取が最大の原因であり、若年~中年男性では肥満による高血圧も増えています。
これらの生活習慣要因が重なり合って発症するのが一次性高血圧です。
一方、二次性高血圧は何らかの病気や異常が原因で起こる高血圧です。
例えば、腎臓の病気(腎炎や腎動脈の狭窄など)やホルモン異常(原発性アルドステロン症、クッシング症候群、甲状腺機能異常など)があると、それが引き金となって血圧が上がります。
また、睡眠時無呼吸症候群でも高血圧を引き起こすことが知られています。
原因疾患を治療すれば血圧が安定する場合も多いため、二次性高血圧が疑われる場合は原因の精査と対処が重要です。
なお、一部の薬剤(ステロイド剤、NSAIDs〔消炎鎮痛薬〕、経口避妊薬など)や過度の飲酒・喫煙も血圧を上昇させる要因となり得ます。
東中野のクリニックで治療を検討している方へ[高血圧の原因・メカニズムとリスク、治療法]|血圧が上がるメカニズム(交感神経系・ホルモン・血管抵抗など)

血圧とは、心臓が送り出す血液が血管壁にかける圧力のことです。
血圧の値は「心臓から送り出される血液量(心拍出量)×血管の抵抗(末梢血管抵抗)」で決まります。
つまり、心拍出量が増えたり全身の血液量が増加すると血圧は上がり、逆に血液量が減ったり血管が拡張すると下がります。
また、動脈硬化などで血管が硬く狭くなると血液が流れにくくなり、血圧が上昇します。
体の中では自律神経やホルモンの働きによって血圧が調節されています。
緊張や興奮などで交感神経が活発になると、末梢の神経末端からノルアドレナリンという物質が分泌され、心臓の鼓動が速く強くなり血管が収縮するため血圧が上昇します。
逆にリラックスしているときは副交感神経(迷走神経)が優位になり、心拍数や心臓の収縮力が抑えられて血圧は低下します。
このように、自律神経系は瞬間瞬間で血圧を調整し、必要に応じて血圧を上げ下げしています。
さらにホルモン(体液性因子)も血圧調節に深く関与しています。
代表的なのが腎臓で調整される レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系(RAA系)と呼ばれる仕組みです。
血圧が低下すると腎臓からレニンが分泌され、連鎖的にアンジオテンシンⅡという物質が作られます。
アンジオテンシンⅡは強力な血管収縮作用を持ち、全身の血管を狭めて血圧を上げると同時に、副腎からアルドステロンというホルモンを出させます。
アルドステロンは腎臓でナトリウム(塩分)と水分を再吸収させる働きがあり、これによって血液量も増えていき結果的に血圧が上昇します。
一方で、体内の水分が不足すると脳下垂体から抗利尿ホルモン(ADH)が分泌されて腎臓で水分を保持し血圧低下を防ぎます。
また心臓からは血圧を下げる作用を持つ心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)が分泌されるなど、複数のホルモンがバランスを取りながら血圧を調整しています。
【参考】
高血圧症の理解に重要な血圧のしくみ
東中野のクリニックで治療を検討している方へ[高血圧の原因・メカニズムとリスク、治療法]|高血圧を放置すると起こりうる健康リスク

高血圧は自覚症状に乏しいため放置されがちですが、そのままクリニックで治療せず何年も経過すると 心臓・脳・腎臓 などの重要な臓器に深刻なダメージを与える恐れがあります。
特に高血圧が長く続くと動脈硬化(血管の老化・硬化)が進みやすくなり、その結果さまざまな合併症リスクが飛躍的に高まります。
- 脳への影響(脳卒中など)
- 高血圧は脳の血管障害、いわゆる 脳卒中(脳血管疾患)の最大の危険因子です。
- 血圧が高い状態が続くと脳の細い血管が傷み、詰まって脳梗塞を起こしたり、逆に血管壁が破れて脳出血を起こすリスクが高まります。
- 実際、日本人の脳卒中の発症・死亡には高血圧が大きく関与しています。
- また、高血圧の人は将来的に認知症を発症しやすいことも指摘されています。
- 心臓への影響(心疾患)
- 血圧が高いと心臓に常に強い負荷がかかるため、徐々に心臓の筋肉が肥大して機能が低下します。
- その結果、狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患(心臓の血管の詰まりによる病気)や、十分に血液を送り出せなくなる心不全を引き起こす可能性が高まります。
- 高血圧の人は心臓発作や心不全による突然死のリスクも上昇します。
- 腎臓への影響(腎不全など)
- 腎臓の細い血管も高血圧によって傷つきやすくなります。
- 高血圧が長期間続くと腎臓のろ過機能が低下し、慢性腎臓病を経て最終的に腎不全(尿が作れなくなる状態)に至るケースもあります。
- 実際、高血圧は糖尿病に次いで腎不全の主要な原因の一つです。
- また腎機能が落ちると前述のRAA系ホルモンの乱れでさらに血圧が上がる悪循環に陥ることがあります。高血圧はこのほか 末梢動脈疾患(手足の動脈硬化による障害)など全身の血管病リスクをそれぞれ数倍に高めることが報告されています。
このように、高血圧を放置すると 脳卒中、心臓病、腎不全 といった命に関わる重大な病気のリスクが大きく増加します。
もしクリニックで高血圧と指摘されたら、症状がなくても早めに対策を講じることが重要です。
東中野のクリニックで治療を検討している方へ[高血圧の原因・メカニズムとリスク、治療法]|高血圧の主な治療法

東中野などでのクリニックにおいて高血圧の治療は、大きく「生活習慣の改善」と「薬物療法」の2本柱で行われます。
高血圧と診断された場合、まずは塩分制限や運動などの生活習慣改善を行い、それでも血圧が高い場合やリスクが高い場合に薬の力を借りる、というのが基本的な方針です。
以下にクリニックでの主な治療法を紹介します。
食事療法(減塩、DASH食、カリウム摂取など)
減塩(塩分制限)は高血圧予防・治療の要です。
日本人の食塩摂取量は多めと言われるため、まず日頃の食事の塩分を見直すことが大切です。
厚生労働省の目標では1日あたり食塩7g未満(女性6.5g未満)を推奨しており、日本高血圧学会は高血圧患者の場合1日6g未満への減塩を強く推奨しています。
例えば味付けを全体的に薄味にしたり、醤油やソースは「かける」のではなく少量を「つける」程度に控える、漬物や味噌汁の量を減らす、といった工夫が有効です。
ラーメンのスープを全部飲み干すとそれだけで5~6gの塩分を摂ってしまうため注意しましょう。
塩分を減らす一方で、カリウム(K)を十分に摂ることも有益です。
カリウムには体内の余分なナトリウム(塩分)を尿中に排泄しやすくする作用があり、血圧を下げる助けになります。
野菜や果物、豆類にカリウムが豊富なので、これらを積極的に食事に取り入れるとよいでしょう(ただし腎臓に持病がある場合はカリウム摂取を制限すべきことがあるのでクリニックの主治医と相談してください)。
また、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルも血圧安定に役立つとされています。
近年では食事全体のバランスを整える「DASH食」にも注目が集まっています。
DASH食とは「Dietary Approaches to Stop Hypertension」の略で、アメリカで高血圧改善のために考案された食事法です。
野菜・果物・低脂肪乳製品などを多く摂り、塩分・脂肪分・糖分を控える食事プランで、2か月続けると収縮期血圧が平均11mmHg低下したという報告もあります。
日本人向けにも応用できる食事法であり、日本高血圧学会のガイドラインにも高血圧患者への食事療法の一つとして掲載されています。
要は「減塩」に加えて野菜や果物からのカリウム等ミネラルと食物繊維を十分に摂取し、バランス良く栄養をとることが高血圧には有効なのです。
塩分排出を促すカリウム・カルシウム・マグネシウムをしっかり摂るDASH食は、無理のない減塩と組み合わせることで高血圧予防・改善に役立つと期待されています。
運動療法(有酸素運動の効果と注意点)
運動療法としては、主に有酸素運動(軽~中等度の全身運動)が勧められます。
適度な運動は血管の機能を改善し、血圧を下げる効果があることが分かっています。
具体的には、息が弾む程度の有酸素運動を毎日30分程度、もしくは週合計で180分以上行うことが推奨されています。
例えばウォーキングや軽いジョギング、サイクリング、水泳、体操など、自分が続けやすいものから始めてみましょう。
運動に慣れていない人でも10分程度の運動を数回に分けて行い、1日の合計が30分になれば効果が期待できます。
継続することで収縮期血圧が数mmHg下がったとの報告もあり、減量効果やストレス解消など様々な健康メリットも得られます。
運動時の注意点として、無理のない範囲で行うことが重要です。高血圧の人は激しい無酸素運動や過度な重量挙上(重いダンベルを持ち上げるような運動)は避けましょう。
息を止めて力むような動作は急激に血圧を上昇させて危険です。
筋力トレーニングをする場合も軽めの負荷から始め、徐々に強度を上げるようにします。
また運動中はこまめな水分補給を心がけ、暑熱環境では特に脱水に注意してください。
持病のある方や高齢の方は、運動を開始する前にクリニックの主治医に相談すると安心です。
血圧が非常に高い段階(Ⅲ度高血圧:収縮期180以上または拡張期110以上)の方や、すでに脳・心臓に合併症(脳卒中後や心疾患)がある方は、まずクリニックで適切な治療を受けて血圧をある程度下げてから運動を始めることが推奨されます。
一般に、Ⅱ度以下の高血圧(160/100未満)で心血管病のない場合に運動療法が有効とされており、リスクが高い場合にはクリニックの主治医の指導の下で安全な運動強度を設定してもらうことが大切です。
安全面に配慮しつつ、有酸素運動を日常に取り入れていきましょう。
薬物療法(日本で一般的に使われる降圧薬)
生活習慣の改善だけでは十分に血圧が下がらない場合や、リスクが高い場合、クリニックでは降圧薬(血圧を下げる薬)による治療が行われます。
高血圧治療薬には作用機序の異なるいくつかの種類があり、患者さんの状態に合わせて選択・併用されます。
主な薬の種類と作用の概要は以下の通りです。
- カルシウム拮抗薬(カルシウムチャネルブロッカー)
- 血管の筋肉細胞内へのカルシウム流入を抑制することで血管を拡張し血圧を下げる薬です。
- 血管平滑筋をゆるめて末梢抵抗を減らす作用があり、日本では比較的多く処方されます。
- 代表例にアムロジピンなどがあり、心臓の拍出力を和らげる作用も持つため狭心症などにも用いられます。
- ARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬)・ACE阻害薬
- どちらも体内のアンジオテンシンⅡという昇圧ホルモンの作用を阻害する薬です。
- ARBはアンジオテンシンⅡが血管に作用する受容体をブロックし、ACE阻害薬はアンジオテンシンⅡ自体の生成を抑えます。
- その結果、血管の収縮や体内の水分貯留を抑えて血圧を下げる効果があります。
- 腎臓の保護作用もあるため、糖尿病や腎症を合併する高血圧に適しています。代表薬にロサルタン(ARB)、エナラプリル(ACE阻害薬)など。
- 利尿薬(水利尿薬、降圧利尿薬)
- 腎臓で塩分(ナトリウム)の再吸収を抑えることで塩分と水分を体外へ排出し、血液量を減らして血圧を下げる薬です。
- 主にサイアザイド系利尿薬(例:ヒドロクロロチアジドなど)が用いられます。
- 利尿作用でむくみの改善にもつながりますが、頻尿や電解質異常に注意が必要です。近年は利尿作用を持つアルドステロン拮抗薬(スピロノラクトンなど)が難治性高血圧に併用されることもあります。
- β(ベータ)遮断薬(βブロッカー)
- 心臓に分布する交感神経の受容体(β受容体)をブロックし、心拍数や心臓の収縮力を抑えて血圧を下げる薬です。
- 心臓にかかる負担を軽減するため、狭心症や不整脈、心不全を合併する高血圧患者によく使われます。
- 代表例にメトプロロール、ビソプロロールなど。喘息のある人には慎重に使用されます。
- α(アルファ)遮断薬(αブロッカー)
- 血管の筋肉にある交感神経受容体(α受容体)をブロックし、末梢血管を拡張させて血圧を下げる薬です。
- 高血圧治療ガイドラインでは第一選択ではありませんが、前立腺肥大症を伴う高血圧などで用いられることがあります。
- 立ちくらみなどの副作用に注意が必要です。
このほか、脳の中枢に作用して交感神経の緊張を下げる中枢性降圧薬(メチルドパやクロニジン)、血管拡張薬(ヒドララジンなど)が使われる場合もあります。
しかし一般的には上述した主要な薬剤(カルシウム拮抗薬、ARB/ACE阻害薬、利尿薬、β遮断薬)が中心となります。
薬物療法では単剤で十分な効果が得られない場合、複数の薬を併用して相乗効果を狙うクリニックもあります。
例えば、利尿薬で体液量を減らしつつカルシウム拮抗薬で血管を拡げる、といった組み合わせです。
ガイドラインでもカルシウム拮抗薬・ARB(またはACE阻害薬)・利尿薬の併用などが推奨されており、患者さん個々の合併症や病態に応じて最適な薬剤選択がなされています。
高血圧の薬は単に血圧の数字を下げるだけでなく、心臓や腎臓といった臓器を保護する目的でも使われます。
クリニックの主治医と相談しながら、継続的に内服してしっかり血圧をコントロールすることが将来の合併症予防につながります。
東中野のクリニックで治療を検討している方へ[高血圧の原因・メカニズムとリスク、治療法]|おわりに

高血圧は「サイレントキラー(静かな殺し屋)」とも呼ばれ、自覚症状がないまま放置すると重大な病気を引き起こす怖い一面があります。
しかし、原因の多くは日々の生活習慣に由来するため、食事の見直しや適度な運動などで予防・改善できる可能性が十分にある生活習慣病でもあります。
塩分を控えめにし野菜や果物をしっかり摂る食生活、そして日常的な運動習慣は、高血圧の予防と改善に非常に効果的です。
まずはできることから生活習慣を改善し、それでも血圧が高い場合には早めに東中野のクリニックで相談しましょう。
医師の指導の下、必要に応じて薬も活用しながら適切に血圧を管理することで、脳卒中や心臓病などのリスクを大幅に減らすことができます。
日々の積み重ねが将来の健康を左右します。高血圧と上手に付き合い、安心して長生きできるよう生活を整えていきましょう。
【参考文献・情報ソース】
厚生労働省 e-ヘルスネット、日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」、循環器専門医監修サイトなど信頼性の高い資料を参照しました。
各種公的機関や学会の情報を基に、一般の方向けに平易な言葉で解説しています。
東中野で土曜日の診察が可能な病院をお探しの方は、以下の記事をご参照ください。
東中野で駅近くの病院をお探しなら、「いたや内科」
東京都中野区東中野3-8-9 東中野医療ビル2階
Googleマップで見る

 クリニック紹介
クリニック紹介
 診療のご案内
診療のご案内
 いたや内科クリニックブログ
いたや内科クリニックブログ


 03-3366-3300
03-3366-3300